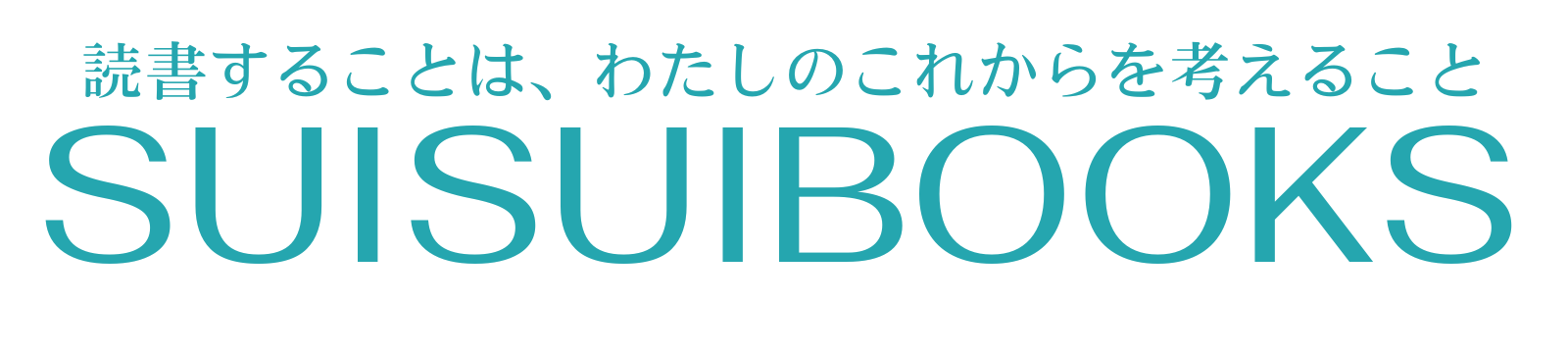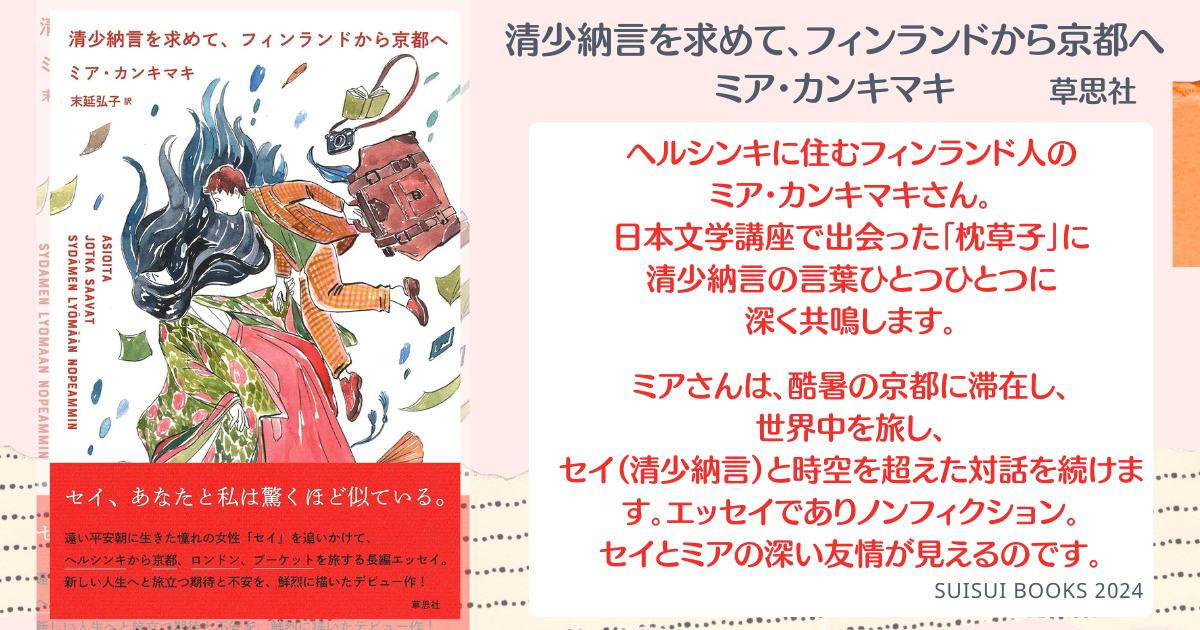『セイ、到着間近。京都へ、あなたの平安京へ降り立つ準備はできつつある』。ミアさんはフィンランドの編集者。生け花の師範でもある、バリバリの日本オタクなのです。彼女は『枕草子』に心酔しています。日本語は解らないけれど枕草子を読み込んで誰よりも清少納言の気持ちがわかる人です。この本を読めばミアさんのセイ(清少納言をそう呼ぶ)への深い愛情と共に、平安京に生きた人々の衣擦れが聞こえてくるようです。2024年の大河ドラマで紫式部が注目されています。ドラマではきっと対抗馬という位置づけになりそうな清少納言のこと、深く知ってみませんか。フィンランドの方がこんなに熱くはまるセイってどんな方なんだろうと。
『清少納言を求めて、フィンランドから京都へ』ミア・カンキマキ 草思社
『枕草子』と出会って京都へ
ヘルシンキに住むミアさんは「日本文学講座」で学んだ『枕草子』に心を掴まれました。当初は固有名詞を使わずに複雑な官位や職業で呼びならわす文体にとても戸惑ったそうです。清少納言の描く、ものや風景、現象をいくつも挙げて網羅するさまに心底共感したそうです。その感覚は現代にも通じるものだったから。
『千年の時を超えて、言葉や文化の違いを超えて、アジア大陸を超えて、古代の平安京から2000年代のヘルシンキにやってきて私の胸に響いたとき、宝物を見つけたと思った。誰もが見逃した宝物を。』
(本文より)
ミアさんはフィンランドで文学者の助成金を申請し、無事に許可を得ます。
『セイ、到着間近。京都へ、あなたの平安京へ降り立つ準備はできつつある』
本文より
ミアさんは夏の長期休暇を利用して日本へ向かいます。そして機内から、セイに語りかけたのが上の一文。どれだけの愛情を持ってセイと向き合っているのかがわかるつぶやきです。
降り立ったのは真夏の京都。灼熱の空気がとどまる盆地のど真ん中。少しでも平安時代を体感するために、快適な宿舎ではなく台所共用の短期滞在型アパートで過ごすことにしたそうです。クーラーもなくて小動物もわんさか出る吉田山のふもとの6畳間がミアさんの京都の住まいです。
『セイ、あなたのことまで気が回らない。』
本文より
きっと平安時代は灼熱ではなかった気もします…。北欧の方が京都の暑さを耐え忍んでいる様子に、同情したりちょっと笑ったりします。
大学での研究ではなく、セイを体感しにきたミアさんは自転車で京都市街を駆け巡り始めました。現存の京都は応仁の乱以降の建造物や文化が多数を占めています。平安時代を体感するのは難しいだろうな、と思うのです。
銀閣寺を訪れたミアさんが静寂と落ち着いた色調に心和ませる段は、平安を少し感じたにちがいありません。
衝撃の事実。『枕草子』原本は存在しない。
現存する世界中の『枕草子』は原本の現代語訳や英訳ではないということ。それを知ったのはミアさんが京都にやってきてしばらくたってからでした。
『あなたを読んだと思う。あなたの文章が残っていないなら、私はいったい何を信じればいいのだろう?』
本文より
恋焦がれた清少納言のこのエッセイ集は本当に存在したのでしょうか。セイが書き留めてから和綴じ本がばらばらになり、それを再編する際に、章が「ごちゃまぜ」なった可能性があるそうです。昔はコピーするには書き写すしかなく、書き損じ、加筆修正が行われても不思議はありません。のちの時代に加筆だと疑われたものを減筆したことも考えられるそうです。そのような学者の見解にミアさんは触れました。当然ミアさんは困惑します。自分の愛したものの根底が覆されたような衝撃だったに違いありません。
しかしミアさんはただの文学好きではありませんでした。彼女の『枕草子』の構成に関する見解はこうです。清少納言はものづくしリストや日記、随筆を章立てて分類していたとは思えない。それは流れるように同時進行で書き上げられたのだと。
『でも、その「ごちゃまぜ」こそが作品の核で、魅力だと思っている人もいる。』
本文より
ミアさんは平安時代の墨書きによる著作の散逸と流布との対比をあげています。それは2000年代以降のインターネットの中で、ごくプライベートな文章が公開され改変され永遠に存在し続けるということ。これは平安と現代を結ぶ共通項なのではないかと考えるのです。
『最終的で完ぺきな作品の本質や意味は霧のように儚い。あなたと私は、それだけが物語を語る方法ではないことを知っている。』
『それでも、セイ、少なくともあなたの名前で印刷された言葉の一部は、おそらくいちばん大事な部分は、あなたの考えから来ているのよね?』
本文より
たとえ順番が入れ替わり、途中が抜け落ち、後世の他者による改変が行われたとしても、清少納言という人物が確かに記した痕跡は生き続け、わたしたちにまで届いているはずだとミアさんは確信するのです。
原本がないことは残念なことではあります。ただミアさんが清少納言の気持ちに分け入り、親しい友人に語りかけるように清少納言の意思に思いを寄せる幾多のシーンがこの本にはあります。友情は世代や国籍だけでなく、時代すら超越するものなんだなと、驚きとてもうらやましく感じるのです。
日本好きの外国人の目から見た京都を共に旅する
ミアさんはセイに倣って、京都滞在で行きたいところしたいことをリストアップしています。真夏の京都に順応してから彼女は中古自転車を買い、碁盤の目をを駆け巡ります。
ミアさんが日本に興味を持つきっかけとなった詩仙堂。この世のものとは思えないほどの静謐さと美しさの寺をとうとう訪れる。『心に宇宙が広がってゆく』。
東山の山腹にひっそりと佇む隠居のための屋敷と庭園ですが、平安時代から続く美意識がそこには根付いています。ミアさんの感受性はそこに反応したに違いありません。

通りがかりの南座で市川海老蔵(現・團十郎)の『義経千本桜』の高額チケットをなぜか買ってしまい、間近で白い狐の演舞を見ることに。忘我の境地となり即座に海老蔵のとりことなったそうです。ミーハーな気質が垣間見えて、セイ全然関係ないなと笑える箇所です。
二条城では、回廊と狩野派の襖絵に感銘を受けます。その近くの神泉苑も訪れたそうです。平安の庭園が唯一残っているといわれているのに、ミアさんはそこでは心が動かなかったといいます。なんでだろうと、読者はちょっと不思議に思うシーンです。

京都御苑(御所)の見学についての章がありました。現存している紫宸殿や清涼殿は平安時代創建ではありません。後世に作られた建造物です。当然清少納言がすごしたのはこの建物ではありません。しかしここでミアとセイの時代を超越した想いの交感がありました。
『セイ、ここにあなたの時代のものが何もなくても、雲がある。』
本文より
樹齢何百年かという松の老木を見て『セイ、あなたは覚えている?』と問いかけるミアさん。雲や樹木に問いかけるなんて。こんなロマンチックな呼びかけがあるでしょうか。
その想いの深さに応えるように清少納言の幻影がミアさんには見えました。後宮の廊下の角を曲がる『ちらりと見えた袖だけ』。
なんだかセイはツンデレだなーと思ってしまいました。
御簾の向こうで交わされる密やかな平安貴族の日常のように、ミアさんが見ることのできたセイの姿はコケティッシュでチャーミング。心が動かされた場面です。
さらにミアさんが屋久島を訪問し樹齢二千年の屋久杉に触れた時『あなたと私をわかつ年数が急に意味のないもののように感じ』たといいます。
森羅万象を味方につけて時空と言語を超えて対話しているのです。2000年もの時代の隔たりはこうしてつながるのですね。
清少納言に関する研究
ミアさんはこの京都滞在の対価として、母国で何らかの結果報告を出さなければなりません。ミアとセイの心の交感だけでは済まされず、ミアさんは博物館や資料館に足を運び、参考文献に目を通します。
そこで愕然としたのは紫式部との情報量の違いです。紫式部に関する書物は内外問わず研究され、現代語訳や翻訳も数多いことはご存知のとおりです。清少納言が登場するのは『紫式部日記』の中での、いけ好かないライバルとしてのみ。。大物作家(紫式部)の論評の中でしか現存していません。『枕草子』の原本すらない状態。情報量が圧倒的に足りない状況で、紫式部の対比としての清少納言は悪評が独り歩きしている状況です。
ミアさんは平安時代の政治の背景にも踏み込み研究を始めました。それは紫式部はいうに及ばず、藤原道長の政治闘争を追いかけることにもつながりました。
ミアさんの著作がどんどん深く冴えわたっていく章なのです。平安時代は道長なくしては成り立たないこともわかりますね。
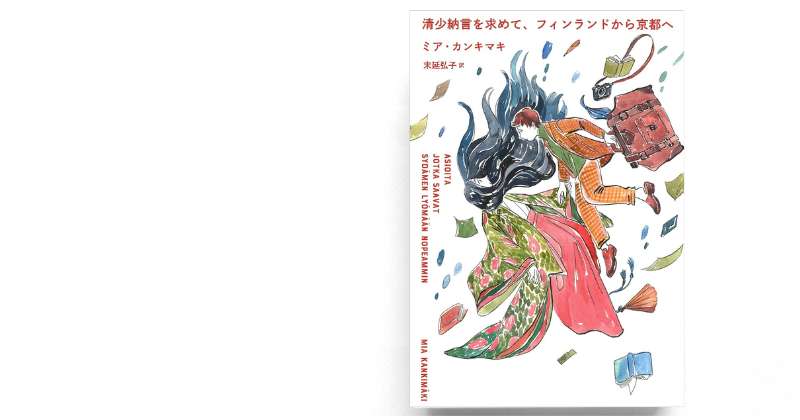
ミアはセイに。私はミアさんに。
ミア・カンキマキさんとはどんな人なんだろう。お会いしたいとも強く感じました。感受性豊かでコケティッシュで想像力にあふれていてちょっと批判的で。きっと清少納言の21世紀における代弁者なのです。
この本が2013年にフィンランドで発表され、特に女性たちの心を鷲掴みにしたのだそうです。日本に対する視線は言うに及ばず、憧れに対して臆せず行動することで未知なる扉が開かれることがあるのです。
2021年の夏、清少納言の母国でこの本が出版され、日本人である私たちもミアさんの情熱を読むことができます。私はミアさんに憧れます。好きなことを深く追求する大切さを教えられました。
ちょっと分厚い本だけれど、ぜひみなさんに読んでもらいたいと思います。ミアさんののめり込み方にちょっと笑って、セイとの友情に心動かされてみてくださいね。