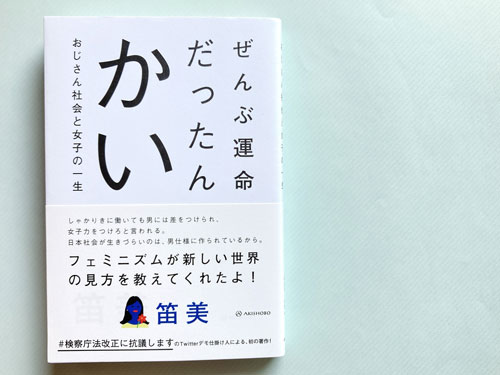笛美(ふえみ)さんは大手広告代理店で働く現役広告クリエイターです。その彼女が検察庁の法改正にツイッターで異議を唱えて、大きなムーブメントとなりました。なぜその場所に至ったのか。男性社会に順応しながら生きてきた彼女が違和感を感じ、フェミニズムに出会うまでのストーリーは、読み手の心も引っかきながら進みます。
『ぜんぶ運命だったんかい おじさん社会と女子の一生』笛美 亜紀書房
2020年5月8日にTwitterに広がった「# 検察庁法改正に抗議します」を作った張本人。ハッシュタグは瞬く間に拡散し、400万を超すツイートを生み出し、Twitterトレンド大賞2020の2位に。現在も広告関連の仕事をしている。(亜紀書房HPより)
大手広告代理店での笛美さんの20代
冒頭、新入社員の笛美さんは高揚感に満ち溢れている。日本を代表する広告代理店の一員となれたのだ。つい張り切りすぎ同期にたしなめられる始末。研修後の飲み会では当然のように「女子は男性社員の隣」で「ビールをつぎ」「料理を取り分け」る。それが「社会人の自覚」ってものなのだ。
CMの組み立てを考えるような花形部署に配属された笛美さんは、「やる気がある」ことを証明するため初日から残業、深夜まで働いてタクシー帰宅。肌もボロボロになりながら仕事をしたそうだ。
こなれてきた笛美さんは、飲み会でのセクハラ発言やボディタッチにもニコニコしている。ホテルの部屋に引き込まれそうになった後ですら、翌朝はお礼メールを送信するとか。男性のセクハラを受け流すのができる社員のあかしだと信じていたという。
過去の自分自身を振り返る第1章第2章は全て「ですます調」。会社に忠実な人間だったことがうかがえる。この辺りを読んでわたしは「あれ?フェミニズム論の棚で選んで買った本だけど、間違えたのかな?」と感じたほどだ。読み手は前時代的な女子力を発揮する笛美さんに、歯をギリギリときしませながら耐えるように読み進まねばならない。
なぜ読み手は”女子力”過多な笛美さんの姿がつらくなるのか。それは自分もそんな行動を取っていた、もしくは現在進行形であるからだ。フェミニズムという言葉も一般的ではなく、「職場の花」「適齢期」「腰かけ」といった若い女性に付帯する単語を受け入れていた時代の女性なら特にそうだ。
自分たちの生き方がどれだけ理不尽であったのかを、笛美さんの実体験を通して理解してしまう。それは悲しくも腹立たしい事実なのだ。
男性と同等に働く、の意味
会議に出席しても何故だか女性の発言はとり上げられない。笛美さんは画策した。自分のアイデアを事前に男性に教えるのだ。その彼が発言することで、間接的に自分の仕事が評価される。実にクレバー。ただ、いいところを全てその男性に譲渡しているのだ。
女性社員として目立ちすぎないように立ち回ってきた笛美さん。彼女が海外の同業他社の人々と交流した時にターニングポイントがやってきた。インドネシアの女性がこう発言したのだ。
「本当は広告賞の審査員も男女半々にするべきです。なぜなら同じ規格でも男性と女性では評価がわかれることがあるからです」
それを聞いた笛美さんの反応はこうだ。彼女はなんて生意気なことを言っているんだろう。半々ではなく男女関係なく実力で決めればいいのだ。と。なぜならうちの会社は平等だからだ。
なぜインドネシアの女性の発言を生意気だと思ったのか。日本の自分の会社には男女差別なんてないと言い切れたのか。のちに思うには”自分が差別を受けている”という認識が全くなかったからなのだ。
笛美さんはたびたび言及しているが、ご自身は受験でも就活でも勝ち組だ。自分の実力でもぎ取ってきたのだ。大きな仕事を任せてもらえる自分は男女関係なく働けていると信じていた。
それは笛美さんが独身で男性社員と同様に仕事ができる環境だったからだ。結婚したって男性は変わらない。笛美さんの言葉を引用すると、
「彼には専業主婦の奥さんがいて、きっと子供も産んでもらえるだろうし、この先もずっとお城にいることができる」「専業主婦の奥さんにサポートしてもらえる男性クリエイターに、私は太刀打ちできるのだろうか?」
平日の昼にきれいな恰好でお買い物を楽しむ専業主婦たちはきっと同僚たちの奥さんなんだ。わたしは30代に突入しようとしていてこんなに焦っているのに。
仕事で実力を発揮している笛美さんが履いているのは「ガラスの靴」。結婚や出産などでそのバランスが崩れたら。お城(会社)に登城できなくなれば、女性の働き手は男性と同等だといえるのか。
心を病んだ日々
周囲の結婚ラッシュに焦燥感を感じた笛美さんは、合コンに参加してみる。男性はハイスペックな彼女の履歴を決して好まないということが分かった。結婚相談所で何度か男性と会うものの、そこにいる彼らとはまず会話が成り立たない。なぜ彼らを夫候補としなければならないのか。
そんな頃、高橋まつりさんが自殺したニュースが駆け巡る。まつりさんが遺したツイッターを読むと、笛美さんが20代の間感じていた男性本位の社会を言語化していた。そして苦しみぬいて亡くなった。まつりさんと笛美さんの何が違ったのか。紙一重の場所でなんとか生きていることを知ることになった。
30代になり自分のことを「産業廃棄物」「羊水がくさっていく」人間なんだと自覚し始めた笛美さん。やばい兆候。上京してよい大学良い会社に入り賞をいくつも獲るような仕事ぶり。自分が男性なら順風満帆なのに、女性であるために何かが欠落したまま歳を重ねていることを恥じている。気が付けば、
「生きていてごめんなさい」
と心でつぶやくようになっていたそうだ。

F国でのインターン生活
精神がボロボロの時期、F国というどうやら北欧の国にインターンに行くことになった笛美さん。なんて渡りに船。彼女は命拾いしたのだと思った。
F国では日本の規律はほぼ存在しないに等しい。短い会議、提案も決定すればそれでよく負けて謝る必要なし、アフター5は家族のため自分のために使う。ジェンダーの平等はもちろん、それぞれの愛情の志向を受け入れ、身体能力を互いに認め合うこと。それがしっかりと根付いた広告表現が求められているそうだ。
日本とは土壌も文化も違うから一足飛びにそのレベルに到達できないだろう。それでも女性が媚を売らず、対等に仕事ができる環境。産むも産まないも個人の自由を尊重してくれる国家。生きやすいに違いない。
フェミニストは「こわいおばさん」くらいの認識だった笛美さんは、フェミニズムが当たり前のF国で、息ができるようになったそうだ。
笛美さん開眼す
日本の雇用環境を調べると、女性がどう対等に仕事をしても結婚出産のフェーズで振り落とされる構造をしている。それはモーレツ会社員を補完する存在であった女性の位置づけが、21世紀になっても変化していないということなのだ。
ここで笛美さんはつぶやく。「ぜんぶ運命だったんかい」。
そしてこの辺りから笛美さんの文体が変化している。丁寧なですます調から、内面の吐露がそのまま文字に載っているような、真摯な言葉になっている。開眼した笛美さんの言葉はじんじんと読み手の私の心を揺さぶっている。
笛美さんは後悔する。「なぜこの社会の構造を疑うことをせず、自分を責め他の女性たちを敵対視してきたんだろう。」と。
働く女性vs専業主婦の構図(「女の敵は女」)は男性がうまくあおった結果だという。私はそれを岡田育さん『我は、おばさん』で読んだ。

女性同士を対立させることにより、世の中の歪んだ構造に目を向けさせない。巧妙なテクニック。その沼にはまっていることに気が付いて声を上げなければ、歪みは正されないのだろう。
フェミニズムに出会った笛美さんは、日本の常識が家父長制に裏付けられた古い体質であったことに気がつく。そして考える。
日本国中にジェンダーギャップの存在を知らしめるには。フェミニストが叩かれ続ける傾向を変えるにはどうすればいいのか。大々的にプロモーションすることができれば一気に認知は高まるだろう。しかしそれは荒唐無稽な技だ。
ジェンダーレスな考え方を念頭に置いた広告はどう作られるべきか。著者は悶々とする。歴代の男性たちが作り上げた王国をひっくり返すことは難しい。彼女は気持ちに抗って仕事を請け負うことが難しくなり、第一線から身を引いたという。
「#検察庁法改正に抗議します」に至るまで
笛美さんの世界にも新型コロナの渦はやってくる。日本の歪みが誰の目にもあらわになってくる。給付金を世帯主に一括支給すると報道された際の違和感。家父長制の考え方の典型例だ。
日本国中が自宅謹慎、新型コロナ一色の報道の陰で、検察庁法改正案がそっと審議され採決されようとしている。安倍政権が自分の保身のために三権分立すら脅かす法案を通そうとしているのだ。ツイッター上でも目立った意見はなさそう。このままだと改正案が通ってしまう。
笛美さんは個人的なツイッターデモとして、#検察庁法改正に抗議します のハッシュタグをつけて放流した。それはフェミニストの人々や野党の人々がリツイートを始め、やがて大きな潮流となっていく。
笛美さんは各媒体の取材に応じる。ただツイッターはおじさん議員たちにはご意見としてカウントされていないらしい。ここで彼女はツイッターで呼びかける。ご自身地元の国会議員にメールやファックスで反対意見を述べましょう、と。
与党も無視できない大きなうねりとなったこの反対運動のおかげか、とうとう改正案廃案となった。
ひとりの人間ができること
大企業で献身的に仕事をこなす一社員だった笛美さんが、心を痛めフェミニズムに出会い、日本のおじさん社会の大本営である国会での動きに影響を与えた。
「見える」と「気づく」は全然ちがう。
笛美さんが本書で何度か上げたキーワードだ。その通りだ。数年前までフェミニズムという単語は知っていても、その内容を知りたいとも思わなかった。掘り下げて考えることもしなかった。それは大きな理不尽に巻き込まれていなかったからだとも思っていた。
ただ思い返せば私も、痴漢に遭遇することも差別的発言をされて食って掛かることもあった。低俗な男個人の問題だと思っていた。これが日本の構造的課題だと分かり始めた時が、私の「気づき」なのだと思う。「女の権利」を声高に主張していた女性たちを冷笑していた自分を叱りたい。
私はまだまだフェミニズムに関する本を読むだろう。それは評論やノンフィクションだけではない。小説の中の女性たちも戦っている。『星を掬う』の主人公はDVと。『砂嵐に星屑』の女性アナウンサーはとうがたったと揶揄されることに全力で抗った。『夏物語』では産むこと生まれた子に対する倫理的な意味を徹底的に掘り下げている。
きっと気がついていないだけで、フェミニズムは発信されているのだ。それをただ消費するのか、隠された意識に「気づく」のか。
大声を出す必要はない。ひとりでわかる範囲で気づいていく。そして少しづつ周囲を変えていく。そのことが重要なのだと、笛美さんから教わった。