伊藤比呂美さんのお名前は『ウマし』で存じていたものの、この本を読んでみようと思わせたのはやはり『閉経記』というエキセントリックなタイトルのおかげだと思います。
老いに差しかかる、いやでもまだまだ!とあらがう時期の50代の比呂美さんのこれぞ赤裸々なエッセイです。
『閉経記』伊藤比呂美 中公文庫 中央公論新社
「漢」と書いてルビは「おんな」と振る。
いわゆる「おばさん」のことを、比呂美さんは漢たちと呼びならわしている。この力強い一文字を使うことで半世紀頑張ってきた自分を肯定できるのだ。
『婦人公論』に連載されていたこのエッセイは、 ”閉経期”前後を生きる女性たちが読者層だ。その同志たちに比呂美さんは誌上で語る。
自分のジャンクな飲み食いについて、体重とエクササイズの関係について、夫との性について、避けて通れぬ老親について。
ともかく書けるだけ書くというスタンスなのだ。
「更年期はおもしろくてたまらない」
冒頭は自身の閉経前後、ホルモン補充療法による多少なりとも穏やかに更年期を乗り切ろうとする体験だ。
鮮烈だった。
「更年期は障害どころじゃない。おもしろくてたまらない」と言い切れる感性。
アレルギーやホットフラッシュ、しみしわ白髪。これらも「観察してみたら、自分は自分であった」とおっしゃる。
その通りなのだ。本当は自分が歩いた道なのだからその老いも含めて迎え入れるべき現象なのだ。ただ老いを割り切れるだけの度胸はない。その山に到達するには自分との闘争ではないだろうか。
著者はその補充療法によって疑似月経を体験する。それは若い時のような「めんどくさい」ものではなく「祝祭的であった」と表現している。
考えればそうなのだ。自分の胎内で子どもを宿す力がまだある証なのだから。疑似ではあるが。
半年ほどの疑似月経のあと、薬を変えて本当の閉経に移行するという。投薬によって暑がりは変わらねど、ホットフラッシュはなかったと比呂美さん。
閉経前の表現が詩人の比呂美さんらしかった。
「遠くから聞こえてくる戦太鼓、あるいは夕立の前にふっとかぎ取る雨のにおい、そんなざわつく気配を感じとった。」
月経の直前の体調変化もまるでワインのテイスティングみたいではないか。多様な表現を知っているということは人生の肯定なのかもしれない。
その「気配」のあと、しめやかな”終わりの月経”が来たというのだ。子宮は自分の大切な同志、ねぎらって人生の転換を迎える大切な儀式のようだった。
(閉経の英単語はなにかな?と調べた時(menopause)、口語では”the change of life”ともいうらしい。前向きな表現だと思う)
一定の年齢になると漢(おんな)は発酵を求めるのかも
紅茶キノコは海外では ”kombucha” と呼ばれているらしい。
説明が前後したが比呂美さんは2度目のご結婚がアメリカ人のだんな様であり、このエッセイ執筆時はカリフォルニアに住んでおられた。
発酵するものはもう一つの人格というか、共生するものだと思う。
比呂美さんは紅茶キノコの瓶をご自身の仕事場において愛でながら育てているという。
『菌の声を聴け』は渡邊格さんのご本のタイトルであるが、
比呂美さんもその耳をすます能力で、菌の声をつぶさに聴きとっている。
紅茶キノコは「昔 流行ったらしい」という認識しかなかったが、調べてみると現役で作っておられるみなさんも多いようす。
元の株(楽天などで売っている)一つ、オーガニックの紅茶を淹れ、紅茶液の10%の砂糖を加え、常温で密封せずにそっと保管する。
うまくいくと発泡し爽やかな酸味のある飲み物になる。その後も発酵を続けるとサルノコシカケ(つまりキノコ)のような平べったいぷるぷるしたものが瓶の中にできる。これが最初に入れた株なのだという。発酵の世界は循環なのだ。
ともかく比呂美さんは発酵の魅力に取りつかれた。
「ただのびんなのに、ものすごく存在感がある。」
「息の音が聞こえるようだ。」
自分の身体との向き合い方もそうだが、発酵するものに対しても一対一での対話を重ねるこの章がとても繊細でよい味わいだと思う。
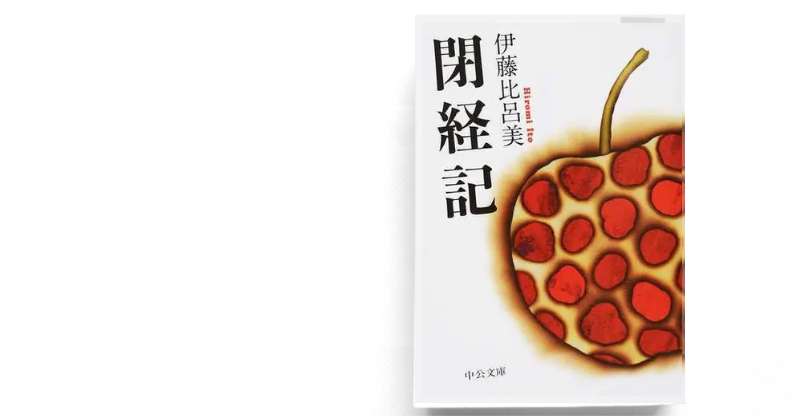
「わが手で生まれていく」塩麹
比呂美さんはジップロックで塩麴を育てている。
「撫でて揉んだ。揉めばもむほど、麹は変化していった。」
「生き物がわが手で生まれていくようであった。」
できあがった塩麴を自分の裁量で漬け、混ぜ、合わせ、さらさらと応用させるのが女、いや漢(おんな)の魅力であり、力強さなのだなと感じる。
融通が利かない自身もこのような発酵にたどり着きたいと思わせる一文なのだ。
さて『閉経記』というタイトルと、発酵によって「わが手で生まれていく」体験は対になっていると考える。
なぜ漢(おんな)はいつの日か菌の声を聴きたくなってくるのか。
女性性の不調の兆しが立ち現れるころ、小動物や植物や発酵食品、自分の介在によって少しでも多く育てたいと思うのかもしれない。
楽々な介護なんてない
カリフォルニアに住む比呂美さんのお父さんは熊本で一人暮らしだ。お母さんが先に亡くなったとのことだ。
(あれ?ブレイディみかこさんちも似た感じ?)
ヘルパーさんがいるとはいえ、月に一度、飛行機を乗り継いで熊本に降り立つという。
朝昼を食べさせ、轟音のテレビを一緒に見る。印象に残る一文がある。
「父のために時間をさく間、カリフォルニアの家では、家族があたしのいない時間を過ごす。」
誰もが無理をして、少しずつ孤独を抱えているんだなと感じる。
さて同世代の漢(おんな)たちと老親についての話題になるそうだ。そこで比呂美さんはなぜか羨ましがられる。
「同居してなくていいよね」「遠くに住んでるからいいよね」「残ったのが父親でよかったね」
気楽な介護をしている人など一人もおらず、みんな苦しみながら老親を介護し生活している。自分の荷物が多すぎて大きすぎて、みな他人の側面など見る余裕がないのだな、とその発言で感じるのだ。
この本の終わりが近づいたころ、その熊本のお父さんが亡くなる。比呂美さんの長女とそのフィアンセが遊びに来て挨拶をした、翌朝だったそうだ。
お父さんは、家族思いでそして寂しがりやだったんだなと思う。できるだけ多くの親族に見送られたのは、遠距離介護を何年も続けた比呂美さんにとっても、せめてもの救いだったのではないだろうか。
あたしたちは満身創痍だ。
最終章で比呂美さんは、女友達について言及する。
夫や両親や子どもとの縁は切っても切れない。けれど、今までつながっている女友達は特別な存在だという。
「あたしたちは満身創痍だ。みんな血まみれの傷だらけ。」
「ぼろぼろになって疲れはてて、それなのに朝が来れば、やおら立ち上がって仕事に出ていく。ふだんは自分が傷ついてることなんか気づいてもない。」
そんな同志たちとひと時会い、近況報告するその時間が心底の癒しになっているのを私も知っている。
この最終章を読んで、老いを周囲を見つめながら優しく強く生きる先輩方の後ろを、私もついていきたいと思えるのだ。



