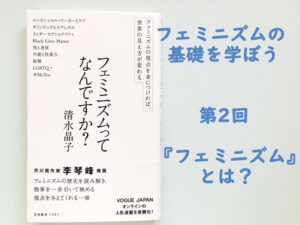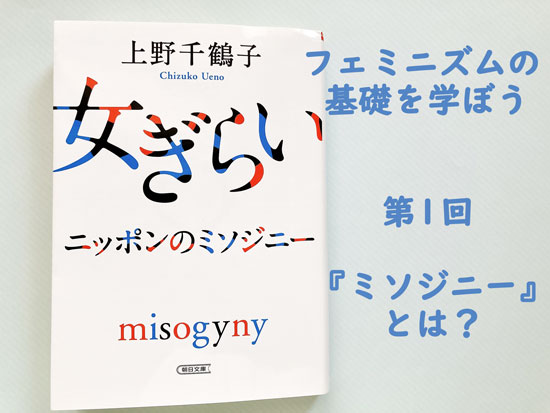ひとまず「ミソジニーってなんですか?」というご質問にお答えしなければ。ミソジニー:女性嫌悪、「女性蔑視」という単語が最適訳とのことです。ジェンダー研究の第一人者上野千鶴子先生の『女ぎらい ニッポンのミソジニー』を今回は取り上げます。ミソジニーとフェミニズム。自分の内なる声が聞き取れるようになるかもしれません。
『女ぎらい ニッポンのミソジニー』上野千鶴子 朝日文庫

- 上野千鶴子(NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)ウェブサイトより)
社会学者・東京大学名誉教授・認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長
富山県生まれ。京都大学大学院社会学博士課程修了。
平安女学院短期大学助教授、シカゴ大学人類学部客員研究員、京都精華大学助教授、国際日本文化研究センター客員助教授、ボン大学客員教授、コロンビア大学客員教授、メキシコ大学院大学客員教授等を経る。1993年東京大学文学部助教授(社会学)、1995年から2011年3月まで、東京大学大学院人文社会系研究科教授。2012年度から2016年度まで、立命館大学特別招聘教授。2011年4月から認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長。
専門は女性学、ジェンダー研究。この分野のパイオニアであり、指導的な理論家のひとり。高齢者の介護とケアも研究テーマとしている。
吉行淳之介から渡辺淳一に連なる文豪たちのミソジニーの系譜
第一章「女好きの男」のミソジニー
上野氏は冒頭から吉行淳之介氏の作品を一刀両断にしている。
「かれの描く世界は、娼婦やくろうと女の世界だ。(中略)女好きのミソジニーの男に共通するのは、娼婦好きということだ。娼婦が好きとは、娼婦を人間として愛するということではない。カネで買った女を自由にもてあそび、ときには本人の自制に反してまでみずからすすんで従わせることが好き、という意味である。」p13
「みずからすすんで従わせる」とはプロの女性に対して”快楽で我を忘れさせる”という通の文化を遂行できる、”粋な男”のことらしい。
その男たちは「性的主体化をとげるためには女という他者に依存しなければならないという背理」を併せ持つ。征服するためには「女という(中略)理解を超えた生きものにその欲望の充足を依存せざるをえないことに対する、男の怨嗟と怒りが女性嫌悪である」と上野氏は説く。
平易に訳すと「男自身が女より優位だと再認識するためには、どうしても女が必要になる」。女なんぞは…と考えているが、その女に接さなければ自分は満たされないという矛盾にいら立っているのだ。
「女の通」として名を馳せた吉行作品を好んだ女性読者は、彼に「女とは」と教授願う形で精読したのかもしれない。それは「女に対する男の妄想である」ことに後になって気がつくのだと。
吉行氏を断じた第一章の最後にこうある。
「男が現実の女から「逃走」して、ヴァーチャルな女に「萌え」るのは、昔も今も同じである。」p26。ここで2020年代の読者はネット上にまき散らかされている、異常な胸囲のお嬢さんのイラストを唾棄と共に思い出す。
現在、吉行氏や渡辺淳一氏のような恋愛に見せかけた男性至上主義を謳歌する小説は影を潜めている。(官能小説は健在だが)。それらを純文学といい、女性の作家を”女流作家”と呼びならわした時代はたいそう息苦しい。ただ今の世が生きやすくなったわけではない。媒体を変えてミソジニー感は立ち現れている。
「女の顔をした息子」。二重の期待を背負った娘たち
第八章 近代のミソジニー
高度経済成長期の少年たち=団塊世代の男子は高学歴を追い求めることで、父親を越えていく。同時期の女子は結婚することで「自分の出身階層を脱けだす階層上昇のチャンスを得る」p149。
だが女子は母となり、夫に幻滅しいらだち愚痴を言い始める。「お父さんのようになるんじゃありませんよ」。
それを聞いて育った息子は母から、父親を超えよという過度の期待をかけられる。上野氏はそれを「返しても返しきれない大きな負債」と表現する。母親の期待を背負い息子たちは疲弊しはじめる。
上野氏がもう一つ指摘するのが、団塊世代である親の経済水準を団塊ジュニア世代が上回ることが難しくなったことだ。有名企業で働き郊外一戸建てで妻と子たちと暮らす、という定型が崩壊し、順路が見通せなくなった。これでは両親を超えられない。
そして女子も男子と同様の教育水準を求められるようになった。結婚だけが人生ではない。となると自分で人生を構築しなければならない。母親は娘にも息子同様の過度の圧力をかけ始める。
「「女の顔をした息子」となり、娘と息子に対する期待のジェンダー差は縮小した。」p150
「母親の娘に対する期待は、息子に対する期待とは違う両義性を持っている。(中略)二重のメッセージ、「息子として成功せよ」と、「娘(=女)として成功せよ」を送っている。」p150
ここを読み、思い浮かべたことがある。現在の女子高の多くは良妻賢母を育てるというよりも、どれだけ著名な大学に生徒を送り込むかに焦点が絞られている。校風や制服に創立当時の牧歌的な名残もあれど、授業はハイペースで、近隣校との偏差値のつばぜり合いも垣間見られる。
その上で、品行方正であれという願いも感じ取れる。女子高のよさは男子の目を気にせず、自由に活動ができることだ。だからといって「女子としてのふるまい」をおろそかにはできないのである。
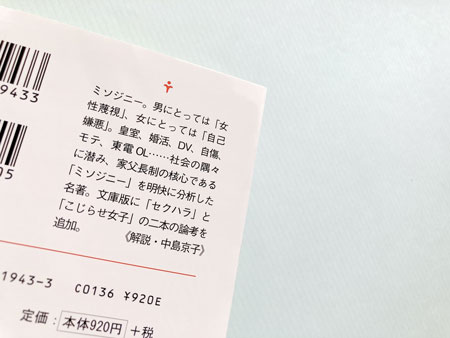
第九章 母と娘のミソジニー
二重のかせを背負った娘たちは、「二代がかりの母の執念」p160 によって大学への進学を果たす。
「「女の子も手に職を」という資格志向は、同時に母親世代の現状認識とそれへの絶望のあらわれでもある。(中略)組織に女の居場所がないことを、結婚前にOL経験のある母世代の彼女らは骨の髄まで身に沁みて知っているからだ。資格さえあれば個人プレーでも生きていける職を、母は娘に勧める。」p160
「OL経験」とはつくづく女限定の言葉だと思う。経験とは一時期の体験にすぎない。男女差なく偏差値だけで順位を決めた学生時代と異なり、社会での”OL経験”によって男性優位社会に辟易する。それが絶望のOL経験だ。男たちと渡り合う社会人となりえた女性以外は、女の限界を抱いてその階段から降りるのだ。
母世代は自身の忸怩たる思いを娘にぶつける。あなたには絶望から遠いところで生きて欲しい。例の「あなたのためを思って」という圧力であり、毒親の第一歩ともいえる。
こうやって娘は母親に疲弊するのだ。疲弊の過程は、読者も歩んできた社会構造に起因するのだと理解する。決して持って生まれた性格だけが女を生きづらくさせているわけではないのだと。
読者が女性なら、自分自身と母親、娘がいるなら自分と娘、その両方の視点で読まざるを得ない章である。さて娘から見たわたくしはどうみえているのか。それを尋ねるのは恐ろしい気がする。
女子校文化は死ぬまで続く女の隠れ家
第十一章 女子校文化とミソジニー
十数人の集まりの座談会で、男性女性がいる場合と、女子限定会の場合での会話はおのずと違ってくる。男性の意見を立てるほどではなくても、話せないこと話したくないことを内心整理してからの会話となるだろう。
女子だけの集まりなら様相は変わる。旧知の知り合いと初対面では距離の取り方に差はあれど、男性が混じっている時とは気分が違う。透明の防護服を一つ脱いだ心持ちと言おうか。それを上野氏はこう表現する。
「男は男同士の世界と、男と共にいるときの女しか、知らない。あたりまえだ。男のいない場所で、女同士が共にいるときに、女がどんなふるまいをするかを知らない。女だけの集まりに男がひとりでも登場すれば、女のふるまい方は即座に変わるから、女だけの世界を男はついに知ることがない。」p194
女の園はさて花園なのかと問われれば、そうではないことを皆知っている。美醜や学力、大人なら経済力や付帯する家族の情報でランク分けが展開されている。安心してさらけ出していいわけではない。その上で男に見せなければならない(と思い込んでいる)配慮・女性らしさなどは脇に置くことができる。
「女子校文化には二重基準(ダブル・スタンダード)がある。男ウケのする価値と、女ウケのする価値とは違う。(中略)男から見て「いい女」と、女から見て「いい女」とが違うのはあたりまえ。男が女に与える価値を女がコントロールすることはできないから、男から見て「いい女」は、女のあいだでは怨嗟と羨望の的になる。」p202
容姿端麗の女性は「美女が老婆に変身する」術を身につけていると上野氏はいう。ネタミソネミからの防御だ。社内一の美人さんが「大型バイクに乗っている」「仕事以外ではジャージ一択だ」とわざわざ言っていたのを思い出した。彼女の防御策だったのだと今ならわかる。それを言わせてしまった自分たちを反省したい。
防御の例に上野氏が挙げたのが藤原紀香氏である。
「女子校のクラスルームに藤原紀香のような美貌と肢体の持ち主、女性性偏差値の高い女がいると考えてみたらよい。(中略)自分を笑いの対象にできなければ、女子校文化のなかで生きていくことはできない。女子校文化の「暗黙知」には、こういう「掟」が含まれる。」p204
上野氏の妄想ノリカは、駅で立ち食いソバを食べている設定になっているのが面白い。実際に藤原紀香氏は神戸の私立女子中高出身だ。自分を”ノリオ”と呼んでいた男気溢れる女子校生だったらしい。その上で、高校野球のイメージガールという非常に男性目線の仕事をしていた。プライベートである学校生活で同級生の妬みをかわすにはどうするか。女子力皆無のがさつさを見せることで周囲の安心と羨望だけを勝ち得たのだろう。
女子校文化とは10代だけのものではない。年齢が上がっても女は女の集まりの中で羽を伸ばす。男への防御と男向けの笑顔は必要としない。”女性らしい細やかな心くばり”という涼やかで奥ゆかしそうなキャッチフレーズなどくそくらえと思っているのである。男目線の価値をうまくはぎ取ることができれば、女同士はもっと連帯すると思うのだ。マウントとってる暇はない。

解説がはばかられる話題をばっさばっさと倒す上野氏
第二章以降のラインナップを見てみよう。
第二章 ホモソーシャル・ホモフォビア・ミソジニー
第三章 性の二重基準と女の分断支配ー「聖女」と「娼婦」という他者化
第四章 「非モテ」のミソジニー
第五章 児童性虐待者のミソジニー
第六章 皇室のミソジニー
…と続く。
ミソジニーと犯罪との関係は深いことも読み取れる。第四章の「非モテ」の段では秋葉原無差別殺傷事件の犯人の心情が語られる。「モテなかった」というどこにでもあるコンプレックス。あの事件に発展するまでの心の動きとミソジニーとの因果関係で、犯罪の種はそこらに転がっているのだと知る。
第六章冒頭。2006年やんごとなき方が御生まれになった、このニュースが日本を駆け巡った時の上野氏の一文はこうである。
「この日ほど、日本列島をそれと名指されないミソジニーが走ったことはない。(中略)もしこれが女児だったら、いったいどんな反応をしただろうか。」p106-107
なるほど。ミソジニーに貴賎なし。掘り下げるには重くて、畏れ多い表題が並ぶ。本郷和人氏に「ジェンダーのおっかないおばちゃん」と揶揄されるほどの第一人者なのだ。女性たちを牽引し続けておられる上野氏の覚悟が読み通せる本となっている。
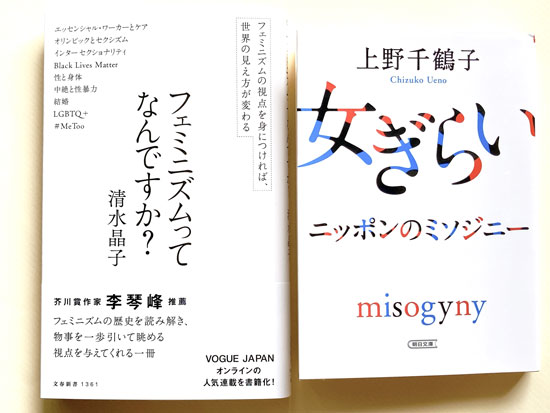
ジェンダー/フェミニズムを根本的に分かっているのか
ジェンダーやフェミニズムに関する本を読みすすめると、自分自身に変化が生じる。テレビや新聞、ラジオにYouTube、対面で見聞きする全ての文章や会話、発生する事件、それらをジェンダー論というフィルターを通して考えているのだ。
当然わたしも幼少から”よき女性とは”という定義を埋め込まれている。わたし自身の声が自分の耳に届いた時に違和感が発生するのだ。自分の中のミソジニー(女性嫌悪)に気がついた時に愕然とする。
上野氏は文庫版増補の中で自身が「ワケ知りオバサン」と化していたことを自省している。
「セクハラにあってショックを受ける女性を「男なんてそんなもんよ」となだめ、下ネタには下ネタでかえすワザを身につけ、男の下心だらけのアプローチをかわしたりいなしたりするテクを「オトナの女の智恵」として若い娘にもすすめる…そんなやり手ババアのような存在になっていたかもしれない。そしてこんなワケ知りオバサンほど、男にとってつごうのよい存在はない。」p346
身に覚えはないだろうか。学校でアルバイト先で職場で、はたまた家庭内で。処世術のように鉄面皮で防御していた自分を思い出さないだろうか。それはわたしが傷つかないための智恵だった。「鈍感さで自分をガードする生存戦略」だったのだ。ディフェンスばかりでは進まないのは自明の理だが、守らなければ私たちの心はズタズタになるではないか。
「そうでもしなければ自分の感受性が守れなかった」p346
上野千鶴子先生にしてこう思うのである。上記の一文を読んで思い出すのは茨木のり子氏の詩である。「自分の感受性ぐらい 自分で守れ ばかものよ」
どうにか自分を守りたい。その上で後続の女性たちが女であることを嫌悪する感情「ミソジニー」を少しでも減らしていきたい。矛盾している。自分が傷つかずに傷ついた女性たちの目安になることなどできるのか。相反する行動を起こしていくこと、それがフェミニズムであろう。男にとって扱いやすい女として安穏と生きて死ねば楽だろうが、それでは女の地位は変わらない。でもどうすればいいのか。
その躊躇と疑問を取り除くためには、ジェンダーの歴史を知る必要があるのではないか。そう考える人々があまたいたのだろう。2022年5月に文春新書から発行されたのが『フェミニズムってなんですか?』。清水晶子氏の書籍である。渡りに船のこの新書を解説したのでご覧いただければと思う。